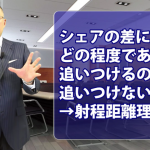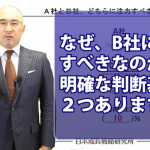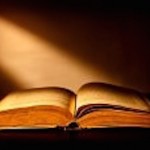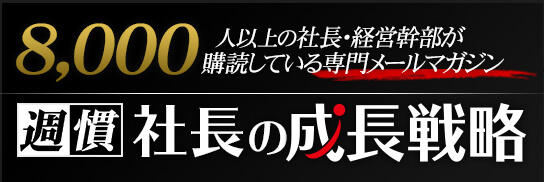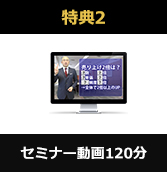ランチェスター戦略の射程距離理論とは?/ランチェスター戦略の理論Vol.11
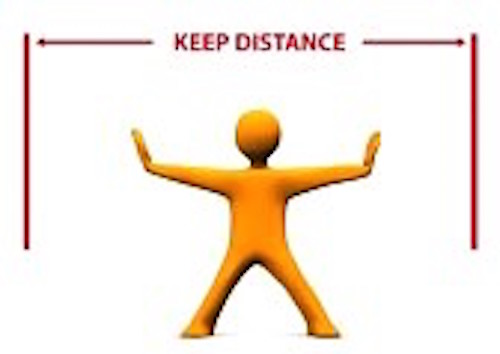
前回は判断基準・目標となるシェアの数値
(7つのシンボル目標数値)をお伝えしました。
ではこれらシェアの数値を基準として
競合をどこまで引き離せば良いのか?
逆にどの程度の差であれば追いつくのか?
その判断基準となる「射程距離理論」をお伝えします。
これはシェアのシンボル目標値から導き出されましたが、
「サンイチの法則」とも言われています。
シェアの目標数値における上限目標値73.9%と
下限目標26.1%を足すと100になり、
その比率を取るとほぼ3:1となります。
(厳密には2.83・・・)
1位の会社が73.9%、2位の会社が26.1%の時(ほぼ3倍)、
前述した戦争理論「クープマンモデル」から導き出された数値上、
その差は埋まらない、勝負あった!
と結論づけることのできる数値となります。
気を付けなければならないのは
第一法則と第二法則で基準とする数値が異なることです。
第一法則下では3倍となっていますが、
これは顧客内の単品シェア、二者間競争の場合に適用されます。
第二法則下では約1.73倍
(第二法則では兵力数が二乗倍なので二乗して3となる√3倍)
の差をつければ逆転は困難と考えます。
この第二法則は第一法則以外となっていますから
競合他社が多い、複数の取扱商品がある場合
にはこちらが該当します。
そう考えると
第一法則のケースは比較的少ないと思いますから、
大半は第二法則で考えてください。
この範囲以上に引き離せば上位のものは安定し、
下位のものは追いつけないということになります。
しかし、
これは絶対ということではありません。
極稀にアサヒビールのようなケースがあるので
「極めて困難」と考えてください。
次回はこの「射程距離理論」の考え方と
前回お伝えした「7つのシンボル目標数値」から
市場シェアがどのような推移で類型化されているのか?
市場における「シェアの類型と推移」をお伝えします。
ランチェスター戦略の射程距離理論に限らず、
集客の仕組み・営業の仕組み・人材育成の仕組み、
最短ルートの成長戦略をもっと知りたい方は
下記のメルマガにご登録ください。
動画・図解付でスマホでも快適に見れるメルマガが届きます。