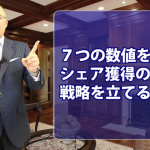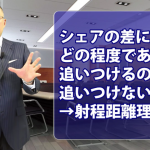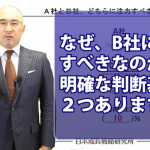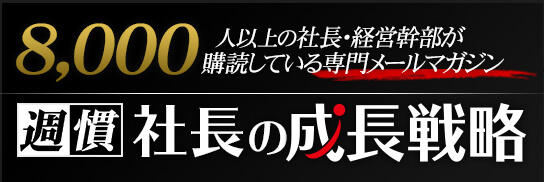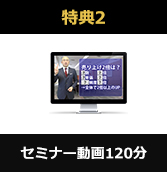ランチェスター戦略、市場シェア7つのシンボル目標数値(上限目標値、安定目標値、下限目標値、上位目標値、影響目標値、存在目標値、拠点目標値)/ランチェスター戦略の理論Vol.10

戦略力2:戦術力1の時、最も戦闘力が高まる!
ということを数式で表したのが「クープマンモデル」でした。
これを元にランチェスター戦略の生みの親である
故・田岡信夫先生と統計学の専門家である斧田太公望先生が
「田岡・斧田シェア理論」を導き出します。
「市場シェアの三大目標数値(3大シンボル数値)」
と言われているものです。
タイトルには「7つのシンボル目標数値」とありますが、
「クープマンモデル」から導き出された「田岡・斧田シェア理論」
の三大目標数値は下記7つの数値の上3つです。
この3つの数値は論理的にも非常に評価が高く、
学者も認めている数値です。
しかし、
この3つの数値だけではシェアがかなり大きくなってしまい、
分散型市場に対応できないため実務上の要請から
更に4つの数値を導き出し「7つの数値」として体系化しました。
これらの数値をどうやって使うかですが、
先ず現在の自社のポジションを確認するということです。
そして短期・中期・長期の経営計画、
シェアアップを目指す時にこれらの数値がひとつの判断基準
となってきます。
ではその数値が何を意味しているのか見ていきましょう。
●上限目標値73.9%
ランチェスター戦略では上限を73.9%としており
100%を求めてはいません。
この数値が既に独占的な数値であること、
更にこれ以上のシェアを獲得しても
安全性・成長性・収益性の面で安定しなくなってしまう
ことがあげられます。
実際の業界でここまでのシェアを取っている企業は
ハンバーガーチェーン業界のマクドナルドが上げられますが、
他にはなかなか見当たりません。
●安定目標値41.7%
50%を安定と思っている人も多いですが、
ランチェスター戦略ではそう捉えていません。
2社間競争であれば50%でも安定しないので73.9%まで必要です。
3社であれば40%でも安定しないかもしれませんが、
ほとんどは4~5社以上の集団の競争になるので
4割を取れば間違いなく1位で、
且つ2位以下をかなり引き離していると言えます。
●下限目標値26.1%
下限と言うのは強者(1位)の下限です。
これを下回ると1位であっても、
その地位は不安定なものになってしまいます。
(その理由は“射程距離理論”によるものです)
この数値はどんなことがあっても生き残ることができる
ギリギリの数値と考えてください。
以下4つの数値は「下限目標数値26.1%」までの
マイルストーンとなります。
●上位目標値19.3%
約20%を獲得できれば上位3位以内に入っています。
この20%は上位の条件になるので弱者が当面目標とする数値です。
ここまでくれば1位も狙えるポジションなので
1位獲得のための戦略に切り替えます。
●影響目標値10.9%
「10%足がかり」と言われ市場参入時の目安となる数値です。
市場全体に影響を与える数値なので、
ここから本格的な競争に突入します。
上位目標値の19.3%までがシェアアップの難所になります。
●存在目標値6.8%
競合に存在を認められる数値ですが、
影響を与えるほどの数値ではありません。
シェア争いが本格化する前の段階なので、
本格的な競争には巻き込まれません。
この段階では競合他社の動きを気にするより、
自社のセールスに注力する時期です。
更に撤退の基準とされる数値でもあります。
●拠点目標値2.8%
市場参入時に最初の一歩を成し得たかを判断する数値です。
数字を丸めると3%→7%→10%となり、
本格的なシェア争いに突入していきます。
このような数値は大企業であれば全国シェアで見ていきますが、
中小企業の場合は競争局面ごとに客内シェア、
地域内シェアというようにセグメントごとにみていきます。
そうした時に最終シェア目標値7割を目指しましょうということです。
全国区で見ればトヨタがそうであったように
4割を取ることができれば先ず間違いなく断トツです。
次回は「射程距離理論」についてお伝えします。
今回お伝えした数値を元に、
どの程度のシェアの差であれば追い付くのか?
どの程度離されたら追い付かないのか?
といった判断基準となるものです。
ランチェスター戦略、市場シェア7つのシンボル目標数値、
(上限目標値、安定目標値、下限目標値、上位目標値、
影響目標値、存在目標値、拠点目標値)に限らず、
集客の仕組み・営業の仕組み・人材育成の仕組み、
最短ルートの成長戦略をもっと知りたい方は
下記のメルマガにご登録ください。
動画・図解付でスマホでも快適に見れるメルマガが届きます。